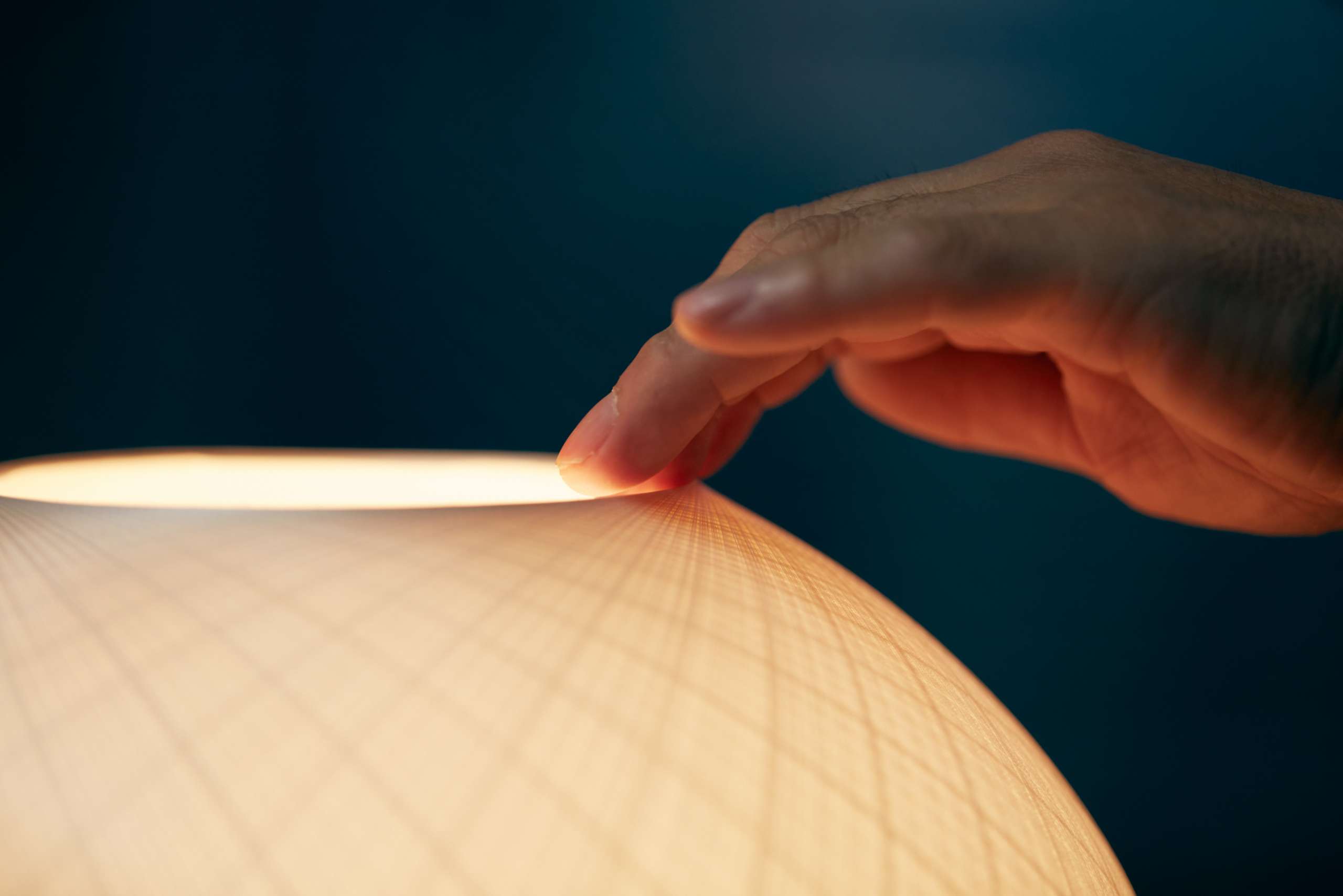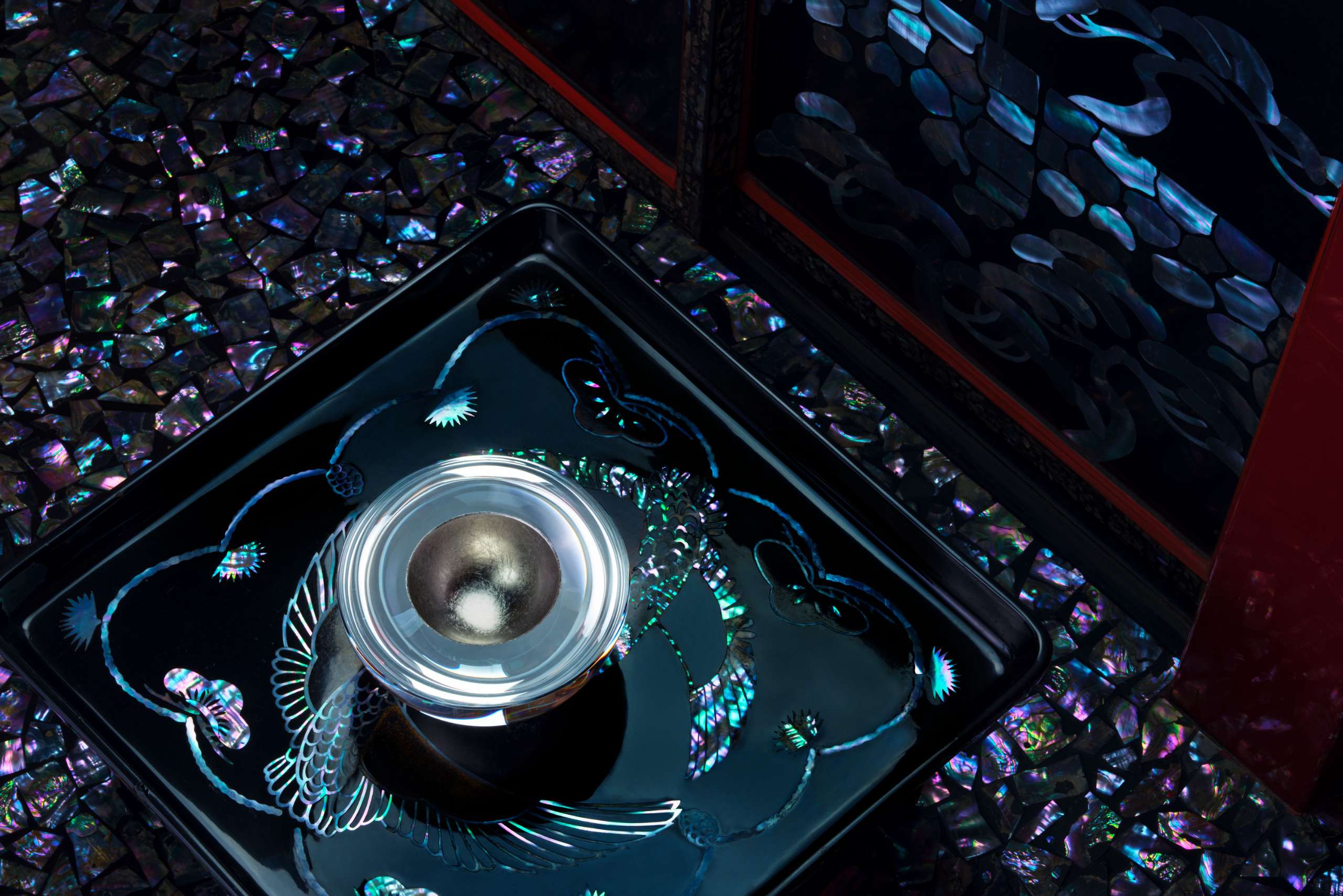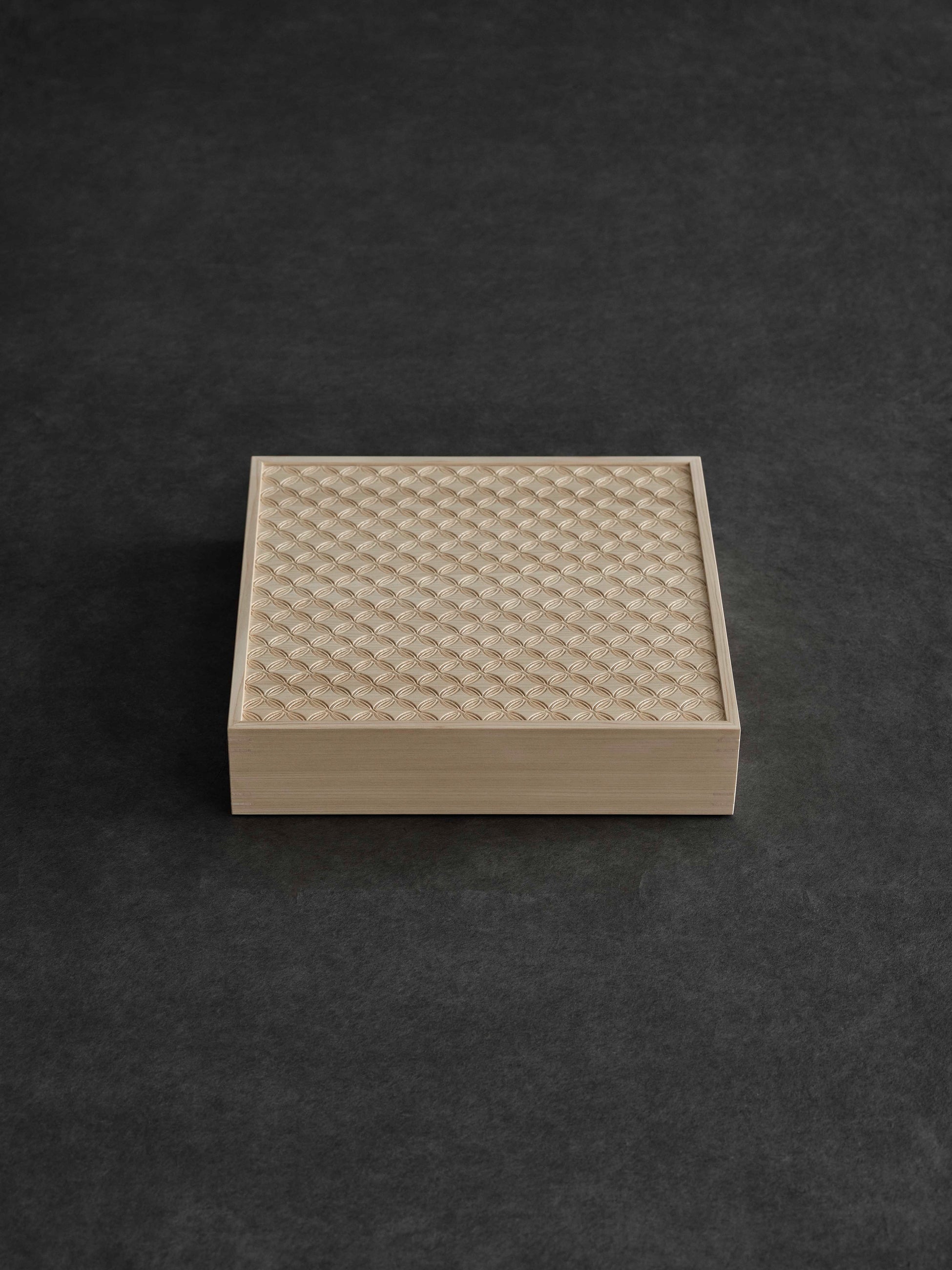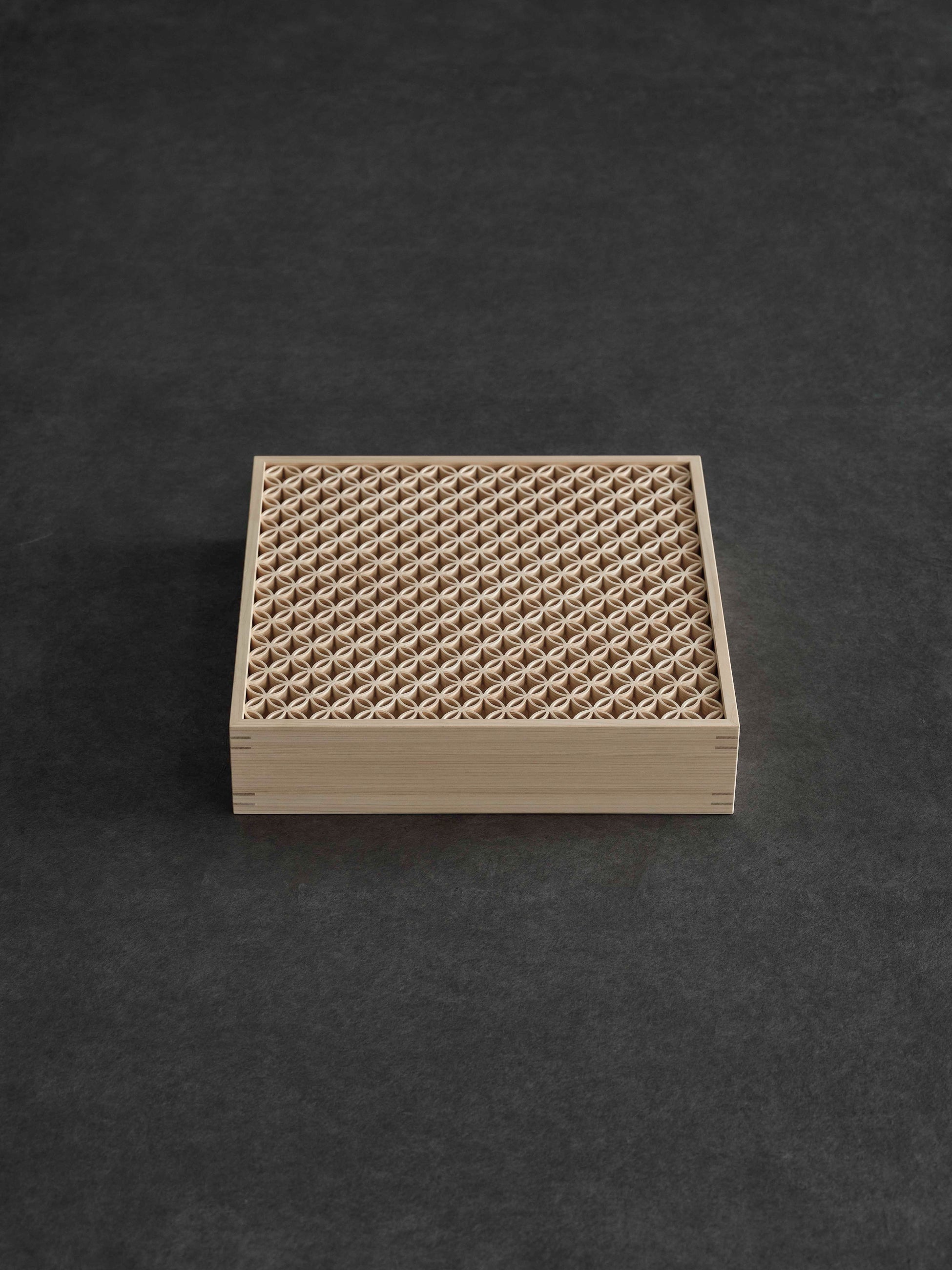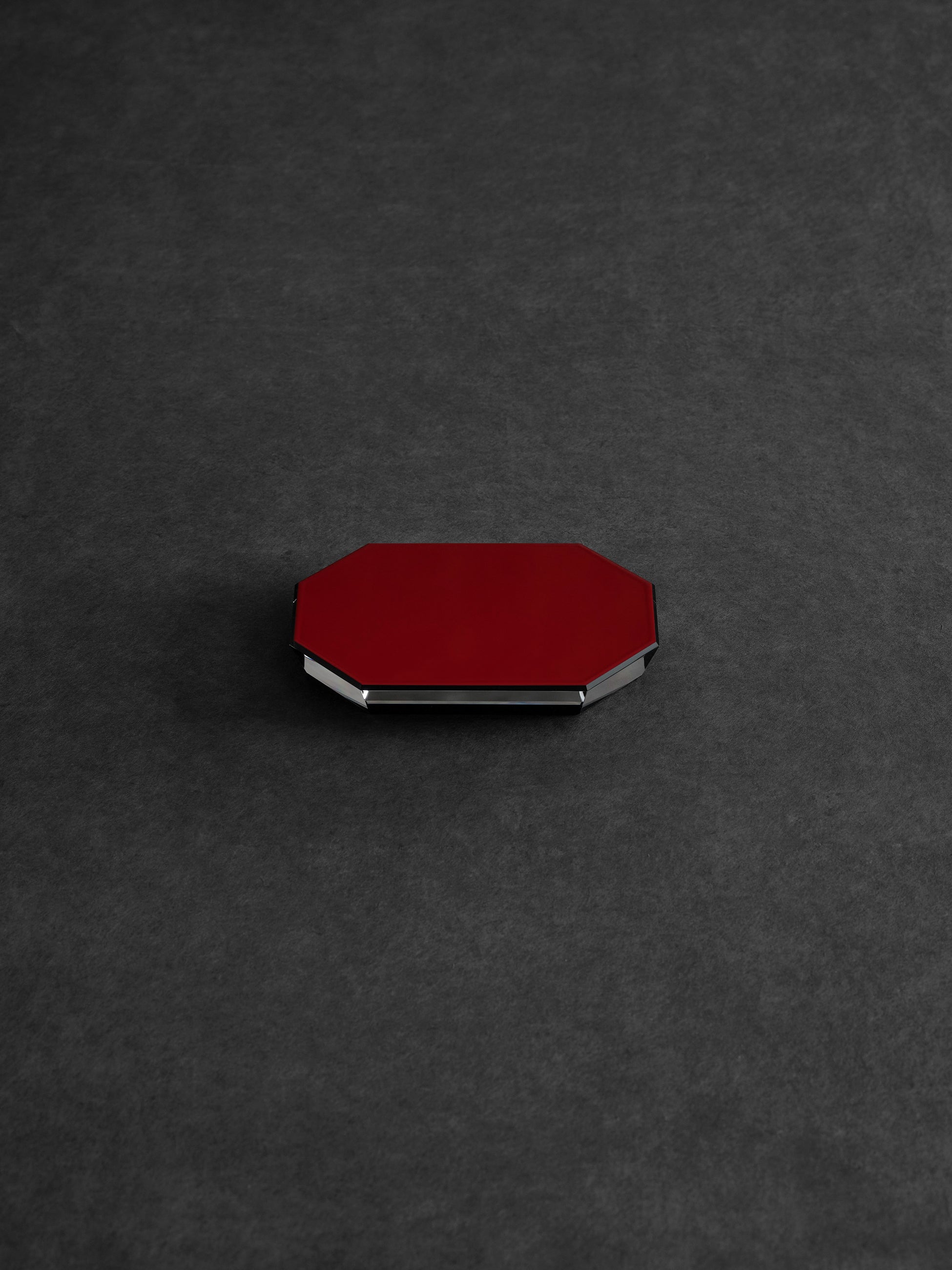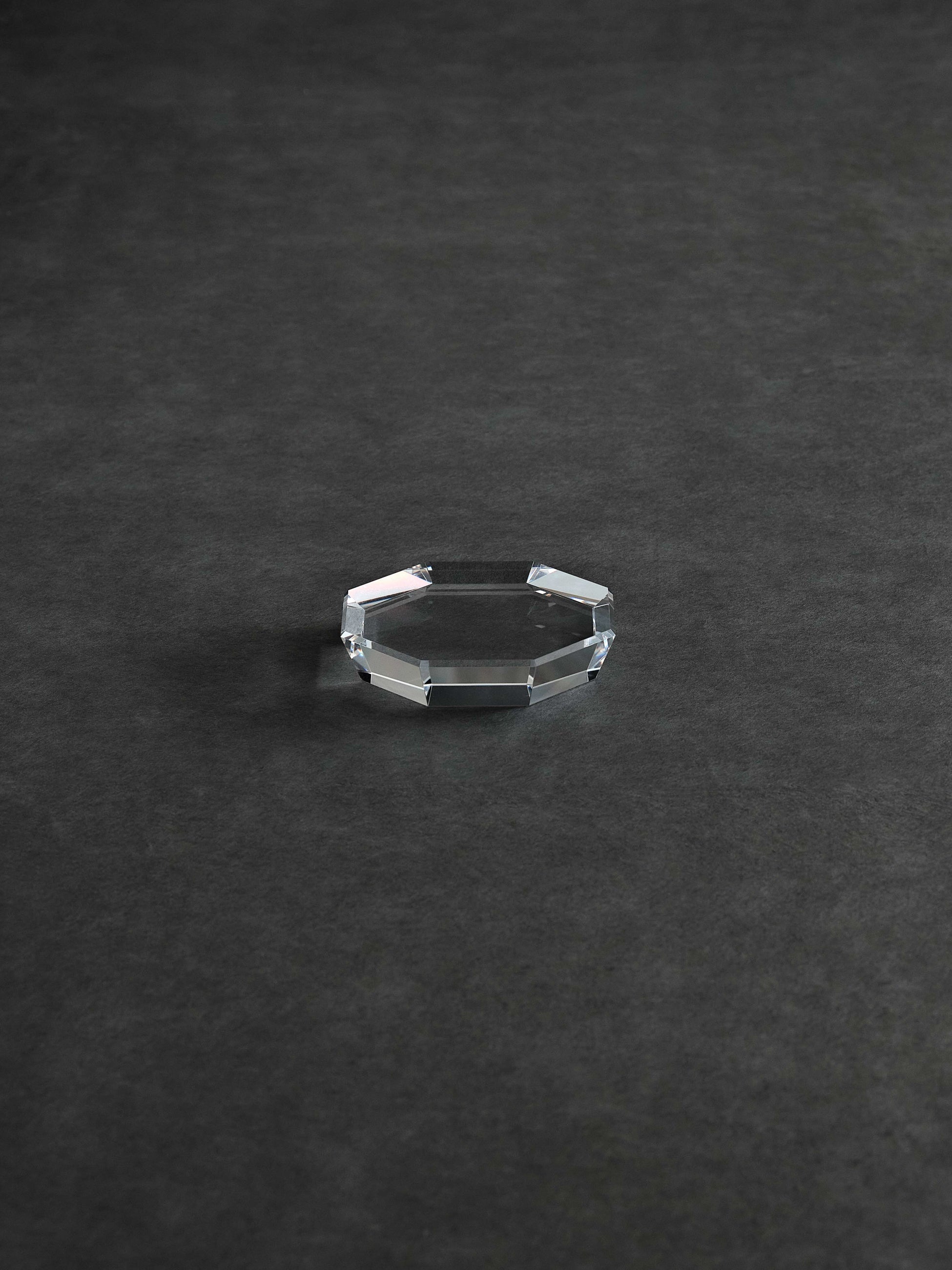PRODUCTS
-

8祝ぐ
Auspicious 8 -

Frill
Frill -

おぼろ
Oboro -

きよみず
Kiyomizu -
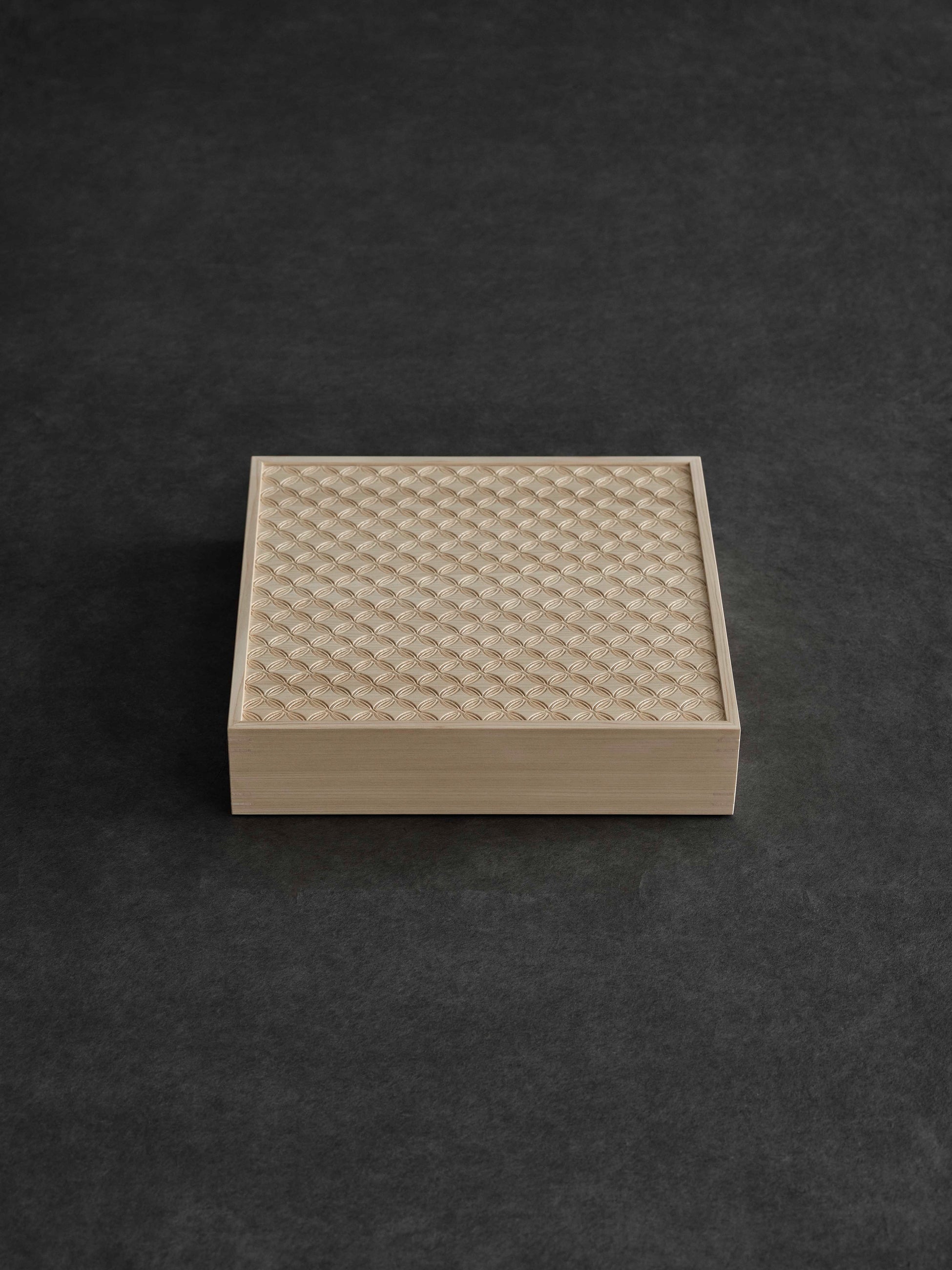
七宝 彫刻
Shippo (carving) -
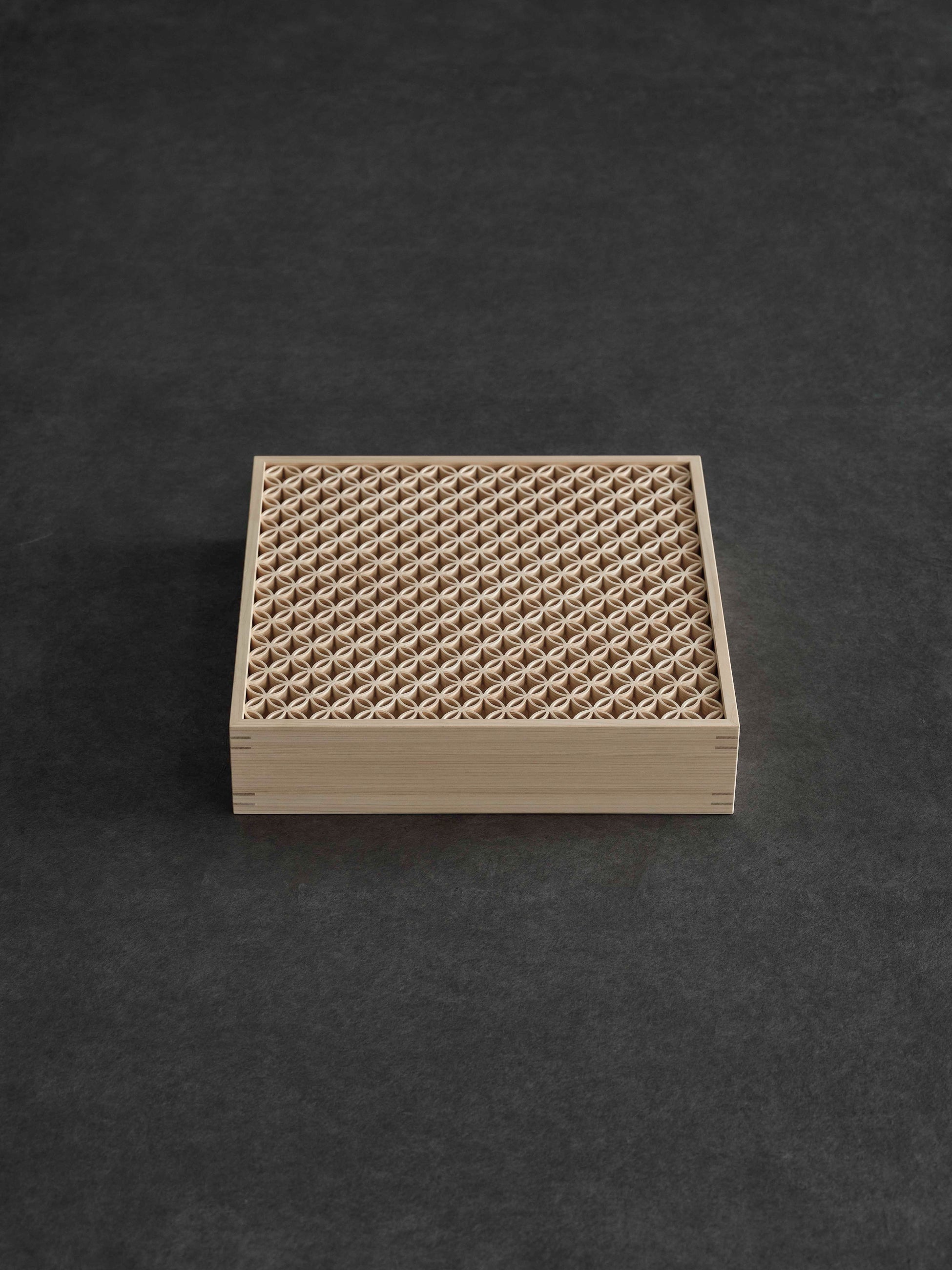
七宝 組子
Shippo (kumiko) -

五輪塔
Gorinto -
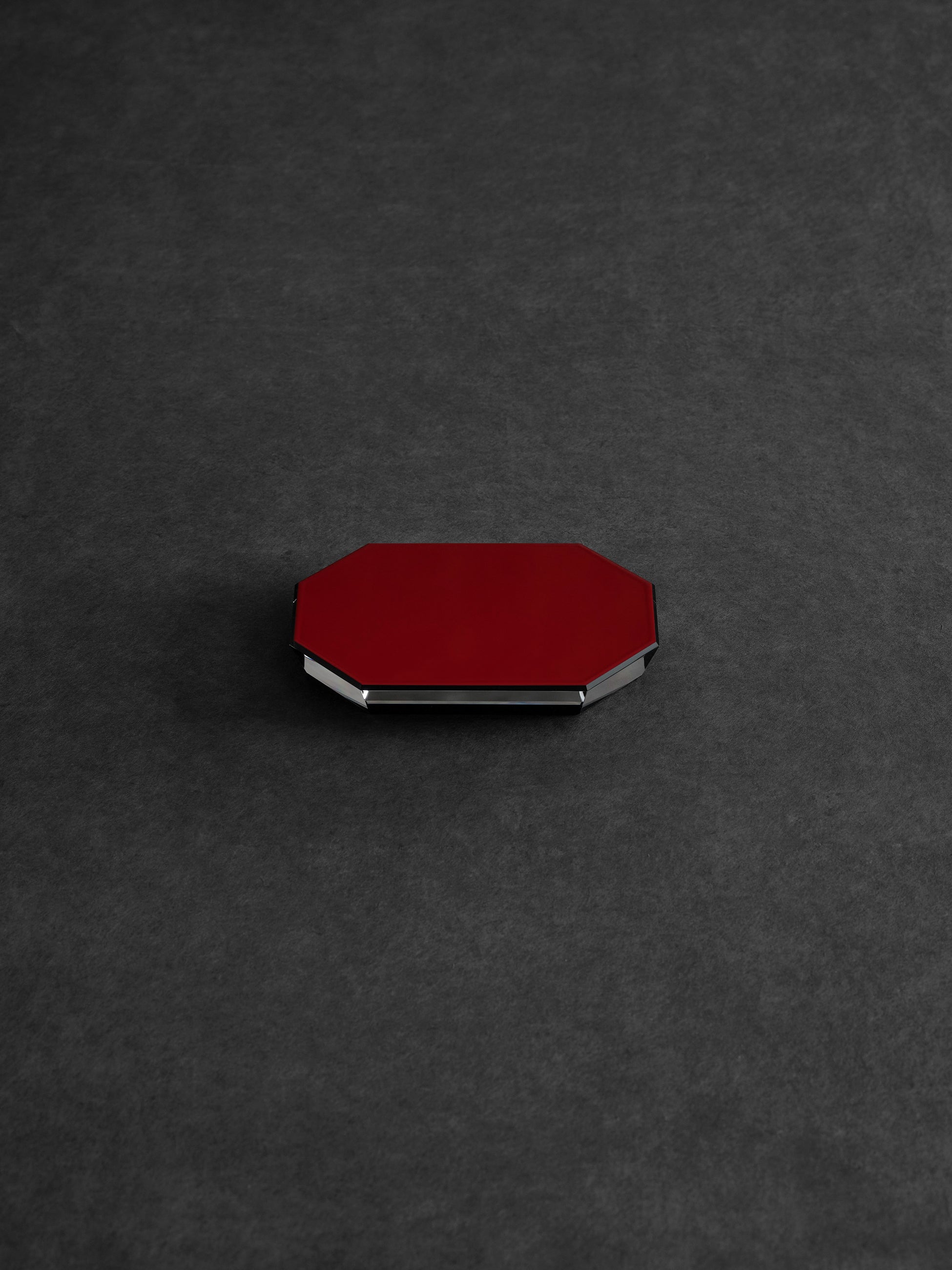
八掛 L
Hakke L -
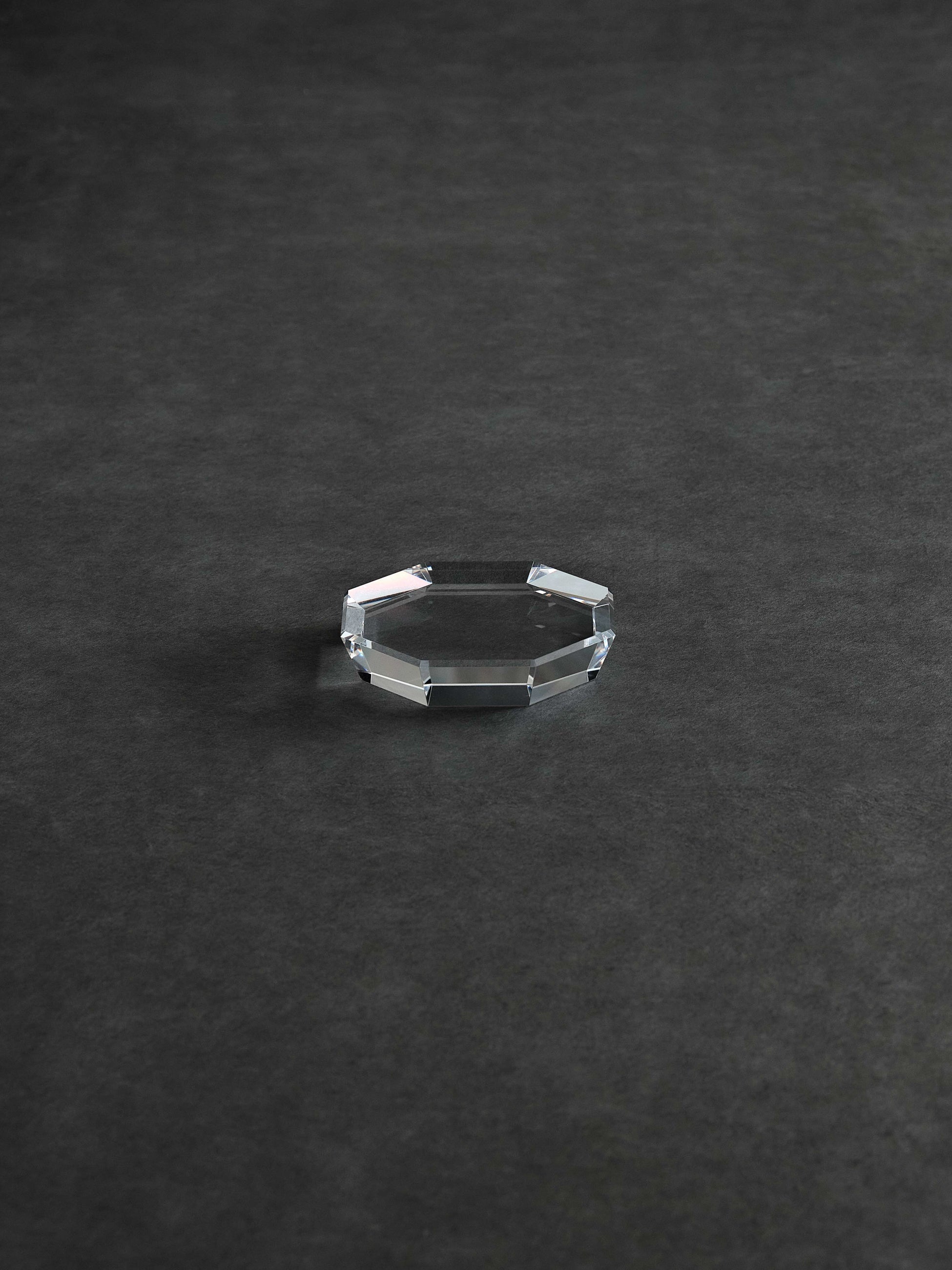
八掛 S
Hakke S -

四分一
Shibuichi -

日月
Hizuki -

綾巻 Pendant light
Ayamaki Pendant light -

綾巻 Stand lignt
Ayamaki Stand light -

関守石
Sekimori -

霰こぼし 庵治石
Arare-koboshi (Aji stone) -

霰こぼし 螺鈿
Arare-koboshi (mother-of-pearl)
GALLERY

編阿弥庵 │ AMUAMI-AN
AMUAMI

立川裕大 │ Yudai Tachikawa